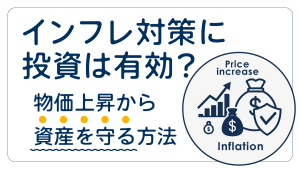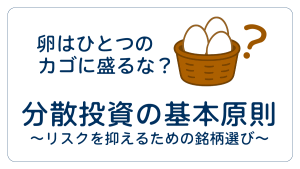デフレ時代にも投資は必要?低金利下での資産運用の考え方

「デフレって、貯金には有利?」そんな疑問、私も抱えていました
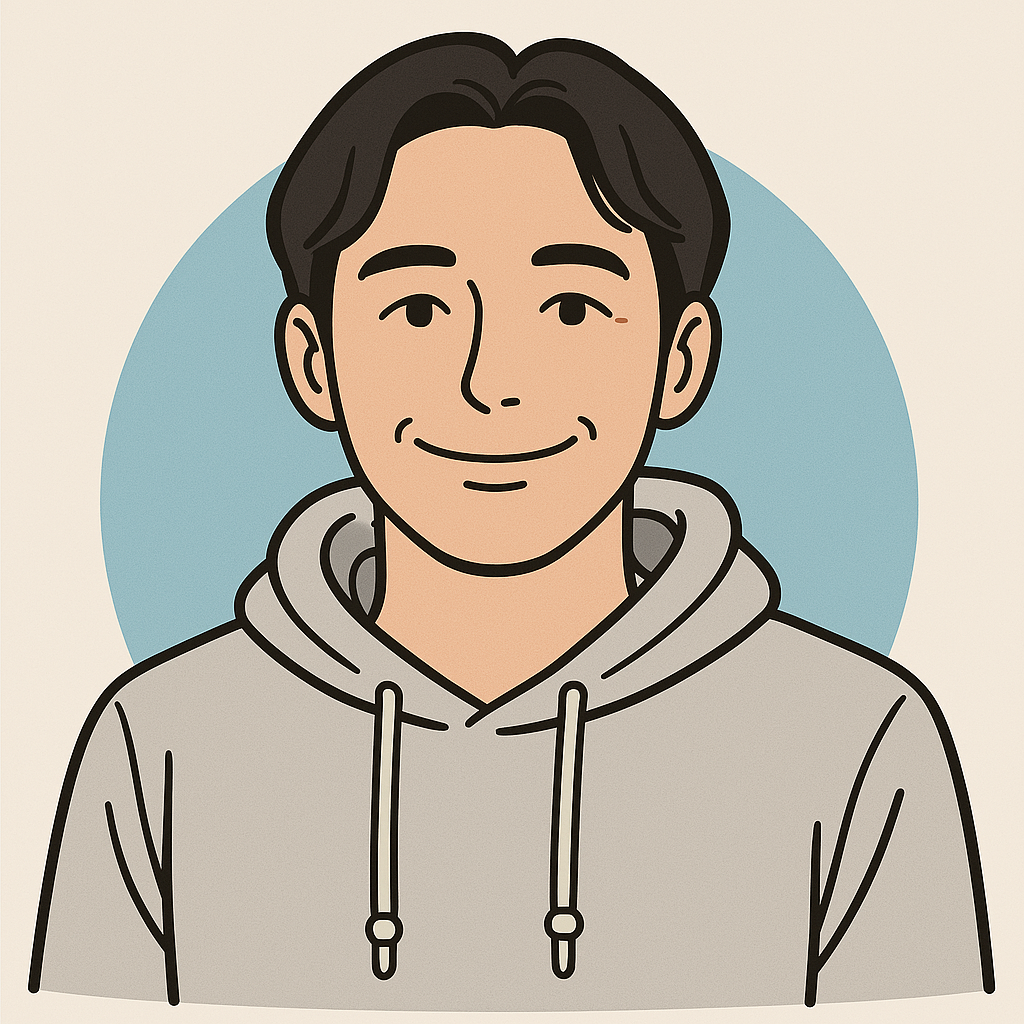
皆さん、日本は長い間「デフレ」の時代が続いていましたよね。物価が上がらず、むしろ下がっていくこともあったので、「貯金していれば、お金の価値が減る心配はないんじゃないか?」そう考えていた方も多いのではないでしょうか。銀行にお金を預けても、ほとんど金利がつかない状況が当たり前になってしまい、「投資なんて、わざわざリスクを冒す必要があるの?」私もそう感じていました。
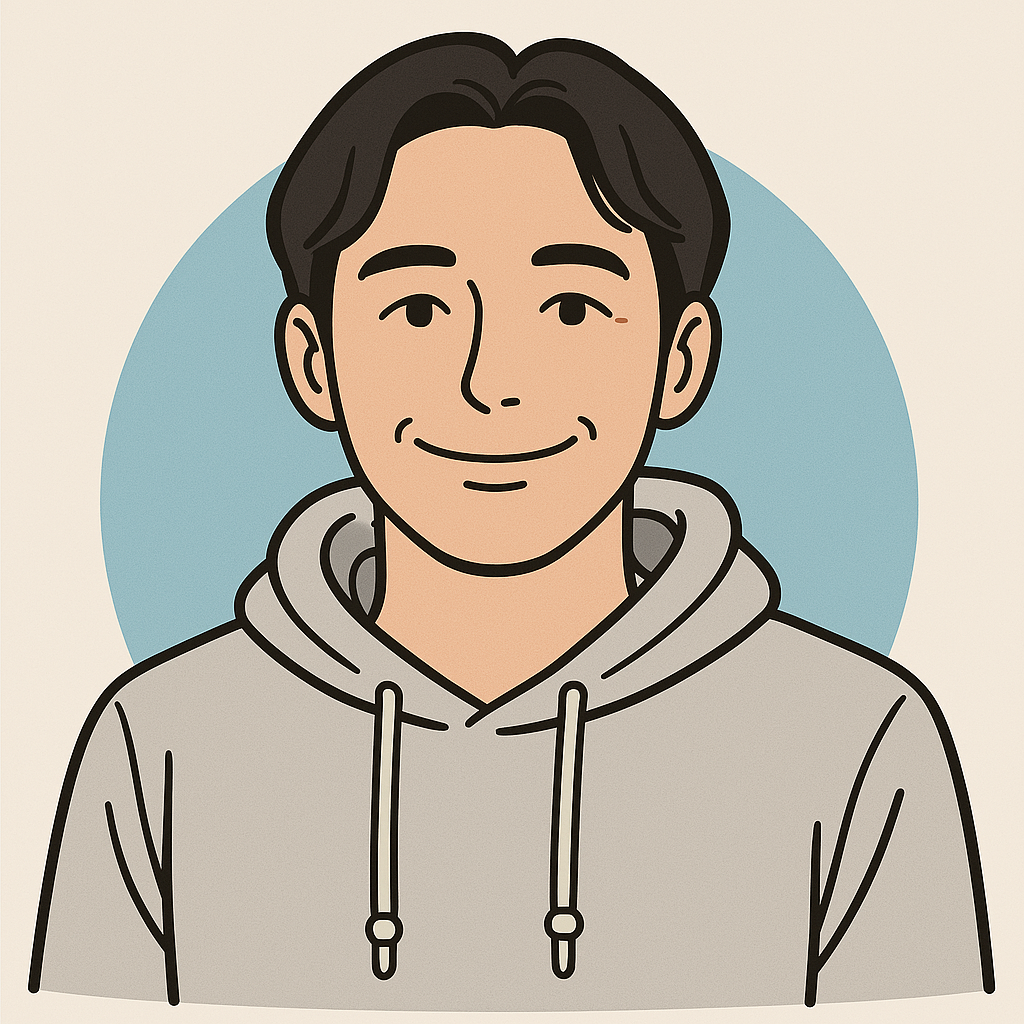
この記事は、まさに「デフレや低金利の時代でも、本当に投資が必要なのか疑問に感じている、私と同じような初心者の方」のために書きました。デフレ環境下での資産運用の考え方を、私と一緒にゼロから学び、漠然とした疑問を解消することが目的です。皆さんが新NISAの非課税メリットを最大限に活かし、どんな時代でも安心して資産形成に取り組めるよう、一緒に考えていきましょう!
デフレと低金利、私たちの資産への影響とは?
まずは、デフレや低金利といった経済状況が、私たちの資産にどう影響するのか、その基本的な仕組みから見ていきましょう。
デフレは「現金最強」の時代?
デフレとは、モノやサービスの値段が全体的に下がっていく現象のことです。例えば、これまで100円で買えていたお菓子が、90円、80円と安くなっていくことですね。
デフレの状況下では、お金の価値が相対的に上がります。つまり、同じ100万円を持っていても、買えるモノの量が増える、という現象が起きます。だから、「デフレ時代は現金を持っているのが一番」という考え方が広まりました。確かに、短期的に見れば、現金を持っていることの安心感はありますよね。私も「とりあえず貯金しておけば大丈夫」という感覚でした。
ずっと続く低金利、その背景は?
デフレと密接に関わっているのが、「低金利」です。物価が下がるデフレ経済では、景気を刺激するために、中央銀行が金利を低く抑える政策をとることが多いんです。企業がお金を借りやすくしたり、私たちがお金を使いやすくなったりして、経済を活発にしようとするわけですね。
その結果、皆さんが銀行に預けている預金の金利も、非常に低い水準に留まってしまいます。残念ながら、銀行に預けているだけでは、ほとんど資産が増えない状況が長く続いてきました。これも、私たち会社員が「このままでいいのかな?」と漠然とした不安を感じる大きな要因の一つですよね。
デフレ時代でも投資が必要な理由
「デフレで現金の価値が上がるなら、貯金でいいんじゃないの?」そう思われるかもしれません。しかし、たとえデフレや低金利の時代であっても、投資が必要な理由はちゃんとあるんです。
1. 将来の「インフレ」に備えるため
経済はずっと同じ状況が続くわけではありません。過去の日本はデフレが続きましたが、近年では物価上昇の兆しが見え始めていますよね。そして、将来的に本格的なインフレが到来する可能性もゼロではありません。
もし、将来インフレが加速した時に、現金や預貯金ばかりだと、その資産の価値が目減りしてしまうリスクがあります。デフレ時代にコツコツと貯めたお金が、いざ使う段になって「あれ?こんなに買えるものが減ってる?」なんてことになったら悲しいですよね。デフレの時期から分散投資を始め、様々な資産に分散して持っておくことが、将来のインフレに備える上で非常に重要なんです。
2. 「金利の高い」海外に目を向ける
日本が低金利であっても、世界に目を向ければ、金利の高い国はたくさんあります。投資信託などを通じて、金利の高い国の債券や、成長著しい海外企業の株式に投資することで、日本国内だけでは得られないリターンを狙うことができます。
私も、当初は日本国内の投資にしか目がいきませんでしたが、海外の成長力を知ってからは、積極的に海外の資産にも投資するようにしています。世界全体で考えれば、経済は常に成長していますからね。
3. 企業の「成長」はデフレでも止まらない
たとえデフレ経済下であっても、成長する企業は存在します。新しい技術やサービスを生み出したり、海外市場で活躍したりする企業は、厳しい経済環境の中でも業績を伸ばし、株価を上げることがあります。
そういった成長企業に投資することで、デフレ下でも資産を増やすことが期待できます。特定の業界や企業に絞るのではなく、幅広い成長企業に分散投資する視点が重要になりますね。
デフレ時代に有効な投資戦略
では、デフレや低金利の時代に、具体的にどのような投資戦略を立てれば良いのでしょうか?
「長期・積立・分散」は普遍的な原則
どんな経済状況であっても、私が皆さんにお伝えしている「長期・積立・分散」は、資産形成の普遍的な原則です。これはデフレ時代でも変わらず有効です。
- 長期:低金利下では短期的なリターンを期待しにくいですが、長期間投資を続けることで、複利の効果を最大限に享受できます。
- 積立:毎月コツコツと投資を続けることで、高値掴みのリスクを分散し、平均購入価格を抑えることができます。
- 分散:国内だけでなく、成長が見込める海外の資産にも分散投資することで、日本国内の低金利・デフレの影響を緩和することができます。
私もこの3つの原則を愚直に守っています。デフレの時期も、インフレの時期も、この原則を続けることで、心のゆとりを持って投資を続けられました。
新NISAで「非課税メリット」を最大限に活かす
デフレや低金利の時代だからこそ、新NISAの非課税メリットを最大限に活用すべきです。わずかなリターンであっても、それが非課税になるのは非常に大きなアドバンテージです。
特に「つみたて投資枠」を使えば、手軽に「長期・積立・分散」を実践できます。デフレや低金利の状況下でも、非課税で効率的に資産を増やしていく道筋を作れるわけですね。
私のデフレ時代の投資経験と専門家の見解
ここで、私自身のデフレ時代の投資経験と、専門家の意見も交えながら、さらに掘り下げてみましょう。
停滞期を乗り越えた私の投資
私が投資を始めたのは、まだデフレの雰囲気が色濃く残る時期でした。正直なところ、当初は資産が大きく増える実感があまりなく、「本当にこれで大丈夫なのかな?」と不安に思うこともありました。しかし、私は「長期・積立・分散」の原則を信じ、愚直に積立投資を続けました。
するとどうでしょう、デフレから少しずつ物価が上昇し始め、経済が上向いてきたときに、それまで積み立ててきた資産が、まさに雪だるま式に増えていくのを実感できました。あの時、焦って止めていたら、今の私の資産はなかったかもしれません。まさに、「耐え忍ぶ時期も大切」だと身をもって学びました。
専門家が示す「ポートフォリオ」の重要性
日本銀行が公表している「生活設計と金融」(2023年)の調査結果では、資産形成において「多様な資産に分散投資することの重要性」が強調されています。たとえ国内がデフレ傾向にあっても、世界全体では経済成長が続いており、日本以外の資産をポートフォリオに組み入れることが推奨されています。
また、金融庁も「資産形成は、一朝一夕でできるものではなく、日々の積立投資を継続することが重要」と示しており、デフレや低金利といった短期的な経済状況に惑わされず、長期的な視点を持つことの重要性を訴えています。これらのデータは、私たち個人の資産形成において、どんな時代でも普遍的な投資の考え方が必要であることを示唆していますね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?「デフレ時代にも投資は必要?」という問いに対し、将来のインフレへの備え、海外の成長を取り込む視点、そして企業の成長に投資することの重要性を解説させていただきました。
「貯金だけではもったいない」という状況は、たとえデフレや低金利の時代であっても変わらないんです。これからの時代を生き抜くために、私たちは「長期・積立・分散」という基本を大切にしながら、どんな経済状況にも対応できる柔軟な資産運用を心がけるべきです。今日から皆さんの資産形成が、より確かなものになるよう、私も応援していますよ!ぜひ、この機会に、低金利下での賢い資産運用の第一歩を踏み出してみませんか?